カラー電子ペーパーは、フロントライトを点けると目に優しいという意味を失ってしまうのでしょうか?
最近、Facebookグループでこんな質問がありました:電子ペーパーは自発光せず、環境光を反射することで目に優しい読書ができるはずなのに、カラー版ではフロントライト[注1]を点けないと画面が見えません。これでは本来の製品コンセプトと違うのではないでしょうか?
また、フロントライトを点けた電子ペーパーは、明るさを最小にしても目が不快で、少しの光でも耐えられないという人もいます。
実はこう考える人は、電子ペーパーが目に優しい理由を自発光しないことだと誤解しています。一般的なスマホやタブレットは発光バックライトが常に目に直接当たるので目に悪い、不快だと思われがちですが、これは誤解です。以下で理由を説明します。
直射光と反射光に違いはない
私たちの目は光を受け取るために生まれつき備わっています。生まれて目を開けた瞬間から、光の刺激を受け続けています。光がなければ物は見えません。ここで疑問が生じます。電子ペーパーが自発光しないなら、どうやって画面が見えるのでしょうか?反射光だから自発光ではないと言う人もいますが、反射した光と発光源からの光に違いはあるのでしょうか?実は両者に違いはありません[注2]。つまり電子ペーパーの表面も確かに発光していますが、その光は環境光の反射です。
もう一度考えてみましょう:反射光は目に直接当たっていないのでしょうか?もしそうなら、電子ペーパーの画面は蜃気楼のようなもの?手を伸ばしてタッチすれば正確にボタンを押せますよね?つまり反射光も目に直接届いていることが分かります。
以上から分かるように、電子ペーパーも常に発光していて、その光は目に直接届いています。ではスマホやタブレットのバックライトが常に発光し、目に直接届くのと何が違うのでしょうか?違いがないなら、なぜ電子ペーパーで長時間読書してもスマホやタブレットより明らかに目が楽なのでしょうか?この答えは後ほど説明します。
フロントライトと環境光に違いはない
次に電子ペーパーのフロントライトについて考えます。フロントライトとは、電子ペーパーの側面上部に設置されたLEDライトで、その光が導光板を通して均一に画面中央に照射され、インク分子に当たり、その光が反射されて私たちの目に届きます。つまりこれも反射光です。この反射光は、天井のLEDライトやデスクライト、太陽光が電子ペーパーに当たって反射される光と何が違うのでしょうか? 室内の照明やデスクライトは環境光ですが、電子ペーパーの表面のライトは環境光ではない?フロントライトと呼べば違うものになる?見分けられるのでしょうか?もし違いが分かると思うなら、以下の写真を見てください:
上記はカラー電子ペーパーBoox Nova 3 Colorのフロントライトあり/なし(環境光のみ)の写真です。どちらがフロントライトを点けているでしょうか?
答えは決まりましたか?
答えを見る
このデモから分かるように、フロントライトと環境光には本質的な違いはありません。背景の明るさを参考にしなければ、フロントライトの有無は分かりません。

|
| 上の図から分かるように、フロントライトも環境光も反射によって色光を目に届けており、違いは一方が画面に近く、もう一方が遠いだけです。 |
フロントライトを点けると目が耐えられないという人もいますが、上記のデモの通り、フロントライトを点けても絶対的な明るさが環境光より暗い場合もあります。むしろ暗いこともあります。フロントライトのわずかな光が耐えられないというのは合理的でしょうか?さらに、カラー電子ペーパーが暗いのはフィルターが環境光の一部を吸収しているからです。ならば、吸収された分をフロントライトで補うべきではないでしょうか?フロントライトをちょうど良く補えば、黒白電子ペーパーと同じくらいの明るさになります。
以上の説明で納得できましたか?
バックライトスマホ・タブレットが目に悪い理由
ではなぜスマホやタブレットは目が痛くなりやすいのでしょうか。これらの直射光源ディスプレイは、バックライトの強度が環境光より強くなければ、色やコントラストが良くなりません。環境光がバックライトより強いと、色やコントラストが落ち、画面が暗くなり、最終的には環境光の鏡面反射に覆われて画面が見えなくなります。これが強い日差しの下でスマホが見えなくなる理由です。だから新しいスマホほど最大輝度を追求します。例えばiPhone 13は最大1200ニトです。これは屋外でも見えやすくするためです。

|
| バックライトスマホは強い光の下で表示品質が非常に悪い |
このため、スマホやタブレットの画面の明るさは常に環境の明るさと乖離しています。画面表面に影ができることもなく、周囲の光の色温度も分かりません。明るさが環境光と乖離すると何が起こるでしょうか?人の目は瞳孔の大きさを調節して光の量をコントロールします。これはカメラの絞りと同じです。なぜ光量を調節する必要があるのか?網膜細胞が受け取れるエネルギーには限度があり、超えると損傷します。だから強い光に遭遇すると反射的に目を閉じて守ります。瞳孔の大きさは環境光によって決まります。

|
| バックライト画面の明るさは環境と乖離しており、暗闇でも懐中電灯のように使える |
ここで問題が分かりますね。目は環境光で瞳孔を調節しますが、スマホやタブレットの明るさで調節するわけではありません。画面は視野の一部しか占めません[注3]。しかし画面は環境光よりずっと明るいので、目の保護機能がこの部分では働かず、強い光を受け続けます。写真で言えば一部が常に高露出状態で、エネルギーを多く吸収します。これが長期的に問題を引き起こすのではないでしょうか?

|
| デスクライトの照明範囲が広く、目の瞳孔が電子ペーパー周囲の光で調節できる |
電子ペーパーが目に優しい理由
フロントライトなしの電子ペーパーは、普通の紙と同じく環境光に完全に溶け込み、環境光の変化に応じて画面の色や明るさも変化します。目も環境の明るさに合わせて瞳孔を調節し、電子ペーパーの光も周囲と同じなので、過剰露出の部分がなく、細胞が過剰なエネルギーを受けることがありません。だから長時間読書しても目に優しいのです。
カラー電子ペーパーは表面にフィルターがあり、サングラスのように環境光の一部を吸収します。そのため画面は周囲より暗くなりますが、これは細胞が受けるエネルギーがさらに少ないことを意味します。文字が判別できるコントラストがあれば、カラー電子ペーパーはさらに目に優しいのです。ただし、紙や黒白電子ペーパーと明るさを比較する人が多いですが、比較しなければ満足しているのに、比較すると明るさが劣ると感じてしまいます。でも絶対的な明るさが読書に不適切かというと、そうでもありません。私はカラー電子ペーパーを1年以上使っていますが、黒白電子ペーパーと併用しても不快に感じたことはありません。むしろ色がある方が気分が良いです。
フロントライトは本当に目に悪い?
カラー電子ペーパーの画面が黒白より暗いのが嫌なら、光を補えばいいだけです。どんな環境光でも構いません。室内の照明を明るくしたり、デスクライトを使ったりできますが、一番手軽なのは内蔵フロントライトです。前述の通り、カラー電子ペーパーの画面は環境光より暗いので、フロントライトの強度をちょうど良く補えば、黒白電子ペーパーと同じくらいの明るさになり、長時間読書しても目に負担はありません。つまり、適切な使い方ならカラー電子ペーパーのフロントライトは目に悪くありません。
ただし例外もあります。フロントライトの明るさがフィルターで吸収された分を超えてしまうと、スマホやタブレットと同じく画面が環境光より明るくなります。色を強調したい(味覚で言えば濃い味付け)ためにフロントライトを最大にすると、スマホやタブレットと同じく目に悪くなります。フロントライトで不快に感じる人は、ほとんどが強度の調整が不適切です。
もう一つ目に悪い状況は、真っ暗な部屋でフロントライトだけで読書する場合です。これは確実に目に悪いです。今のリーダーはフロントライトを最小にしても、真っ暗な環境では画面の明るさが環境と乖離しています。真っ暗なら本来何も見えないはずなのに、見えてしまうのはおかしいですよね?
会議やバスの中など、室内が暗い時にメモや読書をしたい場合、フロントライトを使うしかありません。でも昔は紙の本でどうしていたでしょう?こういう状況ではフロントライトを使うことで目の健康を犠牲にしています。スマホやタブレットはどんな状況でも画面が見える習慣を作りましたが、自然光の下ではこれは正常ではありません。目の健康のためには、こうした習慣を改めるべきです。
なぜ私はフロントライトをほとんど使わないのか?
私の過去の記事を読んだことがある方はご存知かもしれませんが、カラー電子ペーパーを使う時、95%以上はフロントライトを使いません。でもこれはフロントライトに反対しているわけではなく、必要な時は使います。私があまり使わない理由は以下の通りです:
- 普段の読書環境は昼間は採光が十分で、夜はデスクライトを使うので照度不足の問題がありません。
- フロントライトを点けると、光の散乱効果で画面の色の鮮やかさやコントラストが低下します[注4]。設計が悪いと色偏りも起こります。これは以前の記事《カラー電子ペーパーのフロントライトの誤解》、《Boox Nova Air Cのフロントライトを美しく使う方法》で実験しています。興味があればご覧ください。
- フロントライトを点けると消費電力が増え、バッテリー持ちが悪くなります。
- 今のリーダーはほとんど環境光に合わせて自動調整する機能がありません。Hisenseスマホにはありますが、理想的とは言えません[注5]。フロントライトを点けていると、周囲の環境光が変化した時に常に調整しなければならず、集中していると忘れがちですし、頻繁に調整するのは面倒です。むしろ角度や位置を変えて環境光を取り入れる方が楽です。
考えるべき問題
電子ペーパーで記事を書くと目が疲れないので、つい長くなってしまいます。ここまで読んで何か得るものがあれば幸いです。ですが、皆さんが一番考えるべきなのは、読書に必要な明るさとは何か?なぜ多くの人が紙を基準にするのか?黒白電子ペーパーを基準にする人もいます。照明学会の推奨は300~500Luxですが、その根拠は?医学的に最適な照度と証明されているのでしょうか?紙にも種類があり、黒白電子ペーパーにも白さの違いがあり、光によって表面の明るさも変わります。あなたの基準は何ですか?ぜひ考えてみてください。
最後に、スマホやタブレットの画面の明るさが環境光と乖離して目に悪いという理論に医学的な証拠はあるのか?と聞かれることがあります。正直に言うと、ありません!この分野の医学研究は非常に少なく、私は合理的な推論しかできません。だから信じるか信じないかは自由です。少なくとも私は正直に事実を伝えます。iPadのペーパーライクフィルムが本当に目に優しいか分からないのに勧める人とは違います。
でも信じるか信じないかに関わらず、誰かがこの分野の研究をしてくれることを願っています。もしあなたが大学院生や博士課程なら、これは良い論文テーマになるでしょう。人類にも必要な貢献です。特に今、メタバース開発が盛んな時代には、こうした研究が重要です。台湾の医学・工学の融合研究なら、陽交大も良い選択かもしれません。
まとめ
カラー電子ペーパーのフロントライトは、環境の人工照明(デスクライトなど)と本質的に同じで、どちらもインク分子に光を当てて反射した色光が目に届きます。液晶、OLED、Mini/Micro LEDなどのバックライト直射型とは異なります。カラー電子ペーパーはフロントライトを適切に使えば、環境光に溶け込んで快適に読めて目にも優しいですが、適切でないとバックライト画面と同じく目に悪くなります。フロントライトが目に優しいかどうかは、現状では自動調光機能が十分でないため、ユーザーの認識と使い方次第です。
付録
ペーパー類似指数(Paper Similarity Index, PSI)
画面の読書の快適さは、本文で述べた画面の明るさが環境光と融合しているか(環境適応性)以外にも要素があります。ドイツのTÜV Rheinlandは反射型ディスプレイのペーパー類似指数(PSI)を定義しており、スコアが高いほど紙に近い読書体験と快適さになります。興味がある方はTÜV Rheinlandの最近の動画をご覧ください:
電子ペーパー装置のフロントライト開発者への提案
携帯型電子ペーパー装置にフロントライトを設置することで利用シーンが広がりますが、フロントライト設計は目に優しいことが前提であるべきです。ユーザーが適切なフロントライト量を調整できない場合、「フィルター付きカラー電子ペーパー」装置には環境光センサーを搭載し、自動調光が必要です。Hisense A7 CCのようにAutoモードが最低限必要です。どの環境光でどれだけフロントライトが必要かは、Kaleidoごとの反射率特性を研究する必要があります。一般的にAutoモードでは、全暗ならフロントライトは0、300Lux以上ならフロントライトも0です。最大照度は150~200Lux程度で十分で、低照度域での微調整や連続性が重要です。Autoモードではアナログ制御がデジタル制御より良いかもしれません。
また、黒白電子ペーパーに慣れたユーザーは、適切なフロントライトより少し暗い方を好むことが多いので、comfortモードがあると良いでしょう。これはAutoに似ていますが、照度が少し低めです。もちろん好みや目の感度は人それぞれなので、Manual modeも不可欠ですが、Manual modeには機械学習機能があり、ユーザーの好みを記録し、どんな光源下でどの強度かを覚えて、快適さに合わせて調整できると便利です。
冷暖色ライト搭載機種では、同時点灯で白色になるように調整し、色偏りを減らすべきです。暖色ライト搭載機種はnight modeが必要で、night modeでもauto、comfort、manualモードがあるべきです。
最後に、フロントライトの品質や導光の入射角については、E Ink社が研究すべき課題です。主なポイントは有害なブルーライトの削減、色偏りの低減、フロントライト点灯時の色彩の鮮やかさとコントラストの向上です。新世代機種はE Ink ComfortGazeを搭載すべきです。
注釈
注1、原文はバックライトと書かれていますが、電子ペーパーはLCDやLEDのようなバックライト直射型ではなく、画面前面のフロントライトでインク分子を照射し、その反射光が目に届きます。
注2、厳密に言えば、直射光が物体表面で反射する際、反射光の位相や偏光性が変化します。
注3、視野の大部分を占めるには、非常に近くで見る必要があり、焦点が合わないだけでなく、近すぎると長時間の読書で近視になりやすく、距離が近いほどエネルギーも強く(距離の二乗に反比例)、より強い光を吸収しやすくなります。
注4、ただし市場の最新世代kaleido Plus 2は、フロントライト点灯時でも色の鮮やかさやコントラストが非点灯時に近い効果になっています。
注5、Hisenseの良い点は、電子ペーパーの特性に合わせてフロントライトの明るさを調整し、フィルターで吸収された分を補っていることです。ただし36段階しかなく連続性が足りないため、環境光に正確に合わせるのは難しいです。体感ではAutoモードでもやや明るめで、環境光が急変した時の調整速度も遅いです。



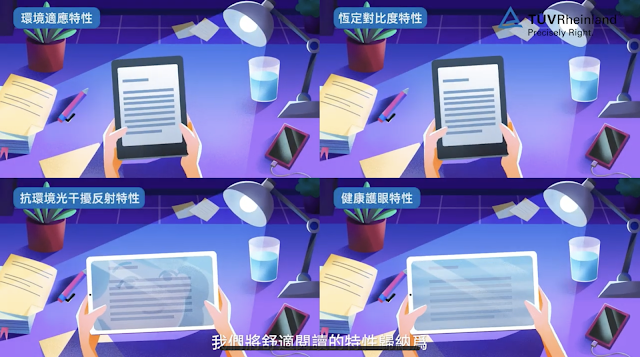









留言
張貼留言